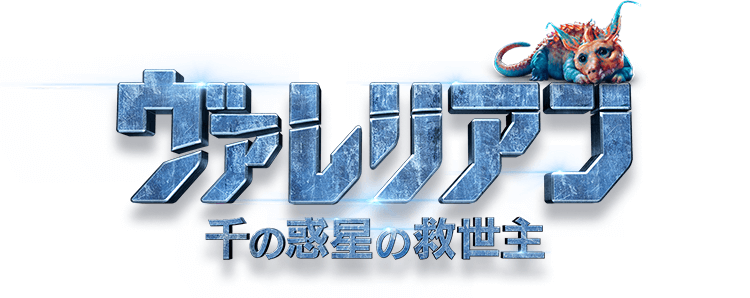
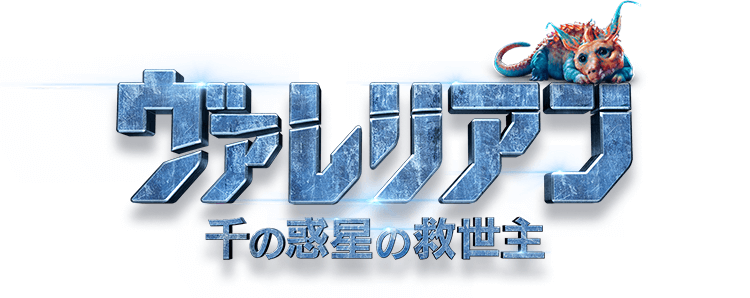
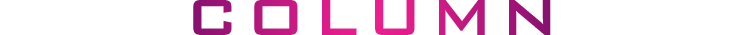
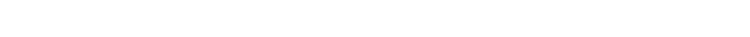 -コラム-
-コラム-
リュック・ベッソンの最新映画『ヴァレリアン 千の惑星の救世主』がついに日本で公開される。凝りに凝った映像とフランス的センス、肩肘張らない娯楽性が同居した、これぞベッソンというエンタメ大作だ。本作には、原作が存在している。ピエール・クリスタン作、ジャン=クロード・メジエール画「ヴァレリアン」。いわゆるバンド・デシネである。
“バンド・デシネ”とはフランス語圏のマンガのこと。直訳すれば、「絵が描かれた帯」という意味で、フランス語の頭文字を取ってBD(ベデまたはベーデー)と呼ばれることもある。マンガと言っても、日本のマンガとは作りがだいぶ異なる。A4版の大きな判型に、ハードカバーの表紙、中面はオールカラーという豪華さ。ページ数は50ページ程度。もちろん例外もかなりあるが、これが基本形で、日本人からしてみると、絵本を思わせる。邦訳は昔からあるが、ここ10年くらいでかなり増えてきた(日本向けに判型を縮小、複数巻を合本というアレンジが施されることが多い)。
フランス語圏に本格的なマンガが誕生したのは、19世紀中ごろ。その頃にはまだバンド・デシネという言葉はない。20世紀に入ると、「タンタンの冒険」など子供向けの有名な作品が誕生する。第二次世界大戦後、さまざまな雑誌が群雄割拠する時代に突入し、本格的な盛り上がりを見せる。バンド・デシネという名称が定着したのもその時代のこと。1959年に「ピロット」という雑誌が創刊されると、さらに人気に拍車がかかった。1960年代後半には、カウンターカルチャーを背景に、子供向けの娯楽にとどまらない作品が次々と世に送り出され、現代につながるバンド・デシネの厚みと多様性が確立される。「ヴァレリアン」が誕生したのは、まさにその時代だった。
1960年代後半以降に台頭した作家には、ギィ・ペラート、ジャン=クロード・フォレスト(「バーバレラ」の作者)、フィリップ・ドリュイエ、メビウス、そして「ヴァレリアン」を描いたジャン=クロード・メジエールなどがいる。これらの若い作家たちは、しばしばSFを通じて、強烈なビジュアル・イマジネーションを叩きつけた。1975年にSFバンド・デシネ誌「メタル・ユルラン」が創刊されると、同誌はたちまち人気を博し、1977年には「ヘビー・メタル」という名前でアメリカに進出、日本も含め、世界中のクリエイターに影響を与えた。折しもSF映画が新たな局面を迎えようとしていた。1975年には、アレハンドロ・ホドロフスキーが「デューン」の映画化企画を立ち上げ、メビウスやH・R・ギーガー、クリス・フォスといったヨーロッパの新しい才能がハリウッドに発見されるきっかけを作った。そして1977年には『スター・ウォーズ』が公開される。アメリカやフランスにおけるSFをめぐる新たな熱気は、雑誌「スターログ」などを通じて、すぐに日本にも波及した。バンド・デシネという言葉が日本でも知られるようになるのは、まさにこの時代である。とりわけ1970年代末から80年代初頭にかけて紹介されたメビウスの衝撃については、大友克洋や谷口ジロー、浦沢直樹、寺田克也といった錚々たるマンガ家・イラストレーターが、さまざまな場所で語っている。
本映画の原作「ヴァレリアン」は、1967年、原作ピエール・クリスタン、作画ジャン=クロード・メジエールの手で誕生。連載先は週刊誌「ピロット」で、当初は「時空警察ヴァレリアン」というタイトルだった。雑誌は1980年代末に廃刊になるが、その後も単行本は描きおろしで刊行され続け、2010年、実に40年以上の歳月を経て21巻で完結。ヴァレリアンとローレリーヌの馴れ初めを描いた0巻とガイド的な22巻を加え、現在は全23巻となっている。SFバンド・デシネを代表するシリーズで、販売部数は累計250万部以上にものぼる。時空警察ヴァレリアンとローレリーヌの宇宙を股にかけたさまざまな冒険を描きつつ、彼らの本拠地である銀河宇宙帝国の首都ギャラクシティの歴史改変による消滅とその復活を語る壮大な物語である。本映画の原作となったのは、主にシリーズ6巻に当たる「影の大使」、そして第2巻「千の惑星の帝国」。前述した通り、1960年代後半以降のバンド・デシネは、その鮮烈なビジュアルで一世を風靡した。メビウスしかり、ドリュイエしかり、エンキ・ビラルしかり。メジエールも例外ではなく、世界中のクリエイターが彼のアートに影響されている。当時のさまざまなSFアートを総合した感のある『スター・ウォーズ』が、やはり「ヴァレリアン」を参照していると言われ、その影響を検証する記事も存在している。それによれば、両者にはビジュアル面において、さまざまな類似が認められる。
「ヴァレリアン」の作画を担当したジャン=クロード・メジエールは、1997年公開の映画『フィフス・エレメント』で、デザイナーとして既にリュック・ベッソンと一緒に仕事をしている。子供の頃から「ヴァレリアン」のファンだったというベッソンのオファーによるもので、そのとき彼はメジエールに、これまでアメリカ映画はメジエールのアイデアを盗用してきたが、今回はメジエールときちんと契約し、対価を支払いたいと述べたのだという。「ヴァレリアン」の映画化は、実はその当時から既に検討されていたらしい。しかし、当時の技術では、「ヴァレリアン」の世界をもっともらしく映画として描くことは不可能だった。それを可能にしたのが、ジェームズ・キャメロンの『アバター』(2009年)に用いられた技術だった。それから8年、『フィフス・エレメント』からは実に20年、ベッソンはついに、フランス映画史上最高額と言われる制作費を注ぎ込み、かつて『スター・ウォーズ』にも影響を与えたバンド・デシネを、『アバター』以降の最新技術を用いて、『ヴァレリアン 千の惑星の救世主』という驚異の映像作品に仕立てあげてみせた。この作品は、バンド・デシネとSFと映画の長い交流の歴史のひとつの到達点であると言っていいだろう。
日本のマンガやアメリカのコミックスと同様に、バンド・デシネにも多くの映画化作品がある。古くは、ロジェ・ヴァディムの『バーバレラ』(1968)。2000年代以降も、エンキ・ビラル『ゴッド・ディーバ』(2004年)からマルジャン・サトラピ、ヴァンサン・パロノー『チキンとプラム ~あるバイオリン弾き、最後の夢~』(2011年)、アブデラティフ・ケシシュ『アデル、ブルーは熱い色』(2013年)まで、幅広い作品が、バンド・デシネを原作に制作されてきた。マルジャン・サトラピ&ヴァンサン・パロノー『ペルセポリス』(2007年)のように劇場用アニメとして話題になった作品もあれば、スティーヴン・スピルバーグ『タンタンの冒険/ユニコーン号の秘密』(2011年)、ラジャ・ゴズネル『スマーフ』(2011)のように、古典的なバンド・デシネがハリウッドで映画化され話題を呼んだケースもある。リュック・ベッソン作品では、『アデル/ファラオと復活の秘薬』(2010年)が、やはりバンド・デシネ原作。今回、古典的名作を原作に、満を持して公開される『ヴァレリアン 千の惑星の救世主』は、バンド・デシネの映画化作品としてはけた外れのスケールを誇る超大作である。

【原作情報】
タイトル:「ヴァレリアン」
著者:ピエール・クリスタン(作)/ジャン=クロード・メジエール(画)
訳者:原正人
仕様:B5変・並製・本文4C・120頁(予定)
定価:2,300円+税
発売予定日:2018年2月7日頃
発売元:小学館集英社プロダクション
